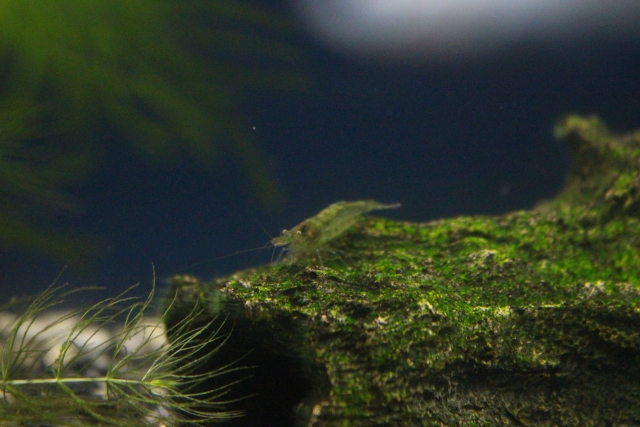生き物を飼うと、繁殖に挑戦したいと思う方も多いですよね。
しかしたくさん増えてしまうと、飼育が難しいこともあります。
増えた爬虫類を無償で引き渡す場合は基本的に自由ですが(特定動物など一部例外あり)、売り渡す場合には動物取扱責任者を置くことが必須です。
あまり聞きなれないものですが、そもそもどんなもので、どうやって取得するのでしょうか?
今回は爬虫類を扱うなら必要になる動物取扱責任者について解説します。
なお公開する内容は2020年8月に動物管理センター等に確認した情報を元に公開していますので、それ以降の法改正等に対応している情報ではないことをご了承の上、詳細は所管の自治体等に確認するようお願い致します。
動物取扱責任者とは?
昨今、ペットとしてさまざまな動物が取引されるようになり、それに付帯するトラブルも多くなってきました。
それに際して動物の取引や管理などを法律で規制し、一定の基準を設け始めているのが日本の現状で、その中で制定されたのが「動物取扱責任者」です。
というのはおおよそ理解していると思いますが、その実どのようなものなのでしょうか。
動物を扱う事業所の責任者を決めるルール
動物取扱責任者とは、簡単に言えばペットショップなど生き物を扱う事業所に、動物の取り扱いについて知識と経験がある人を置こうというルールです。
生き物を取り扱う事業所とは具体的に、
- 販売業(ペットショップなど)
- 保管業(ペットホテル・トリミングなど)
- 貸し出し業(移動動物園やペットタレントなど)
- 訓練業(乗馬施設など)
- 展示業(動物園など)
- 競り斡旋(動物オークションなど)
- 譲受飼養(老犬ホームなど)
以上のような業態を指します。
対象になる生き物は哺乳類、鳥類、爬虫類などで、熱帯魚に関しては現状必要ありません。
誰でも動物取扱責任者になれるわけではない
では、例えばこれから爬虫類を販売したいという場合に、自分が動物取扱責任者になり、動物取扱業を始めよう!とスムーズにいくかといえば、そうはいきません。
知識と経験を証明するために、2020年6月の法改正以降、「行う予定の業種の実務経験」と、「資格等」が必須になりました。
例えば今回例にとっている「買っている爬虫類を繁殖させたいのでその一部を販売したい」という場合には、爬虫類を扱うペットショップなどで半年以上販売と管理に従事したうえで、所定の資格の取得などが一例です。
資格に関しては詳細は下記しますが、もっとも広く取得されているのは「愛玩動物飼養管理士」などでしょう。
ちなみに動物の取り扱いに関して学べる学校を卒業している場合はそれが資格になるそうですが、筆者は独学と実地だったので詳細は不明です。
今回は爬虫類を前提に解説していますので、もし犬猫や馬などを扱いたい場合はあまり参考にならない可能性が高いため、必ず一度事業を始める予定の場所を管轄する動物管理センターに確認を取るようにしてください。
その実、意味はあるの?
余談ですが、実際にこの規則に意味はあるのかというと、これまではほとんどなかった、というのが私の実感です。
というのも私が実際に従事していたときは、現在のように資格が必須ではなく、実務経験だけで動物取扱責任者になれていたからです。
つまり、例えば動物取扱業をして登録しているホームセンターに努めていたけど、実際にはほとんど管理を手掛けていないという人材も、動物取扱責任者をやって販売の許可を得られていたからです。
実際支店を作るために名ばかり責任者を置くというようなパターンは多々耳にしました。
しかし2020年6月の法改正で今は「資格」が必須になったため、こういった行為はできなくなり、私の住んでいる地域では、ホームセンターで爬虫類の取り扱いをやめ、熱帯魚だけの取り扱いになったところもあるという状況です。
まだ2か月しか経っていないためその効果のほどは明らかではありませんが、すでに爬虫類の販売を取りやめる事業者がいるのも事実で、まったく意味のない改正ではなかったといえます。
しかし、動物取扱責任者がどれだけ直接動物の管理を行う業務に従事する必要があるのかなどは規定されていないため、実際には資格勉強だけした名ばかり責任者を置けないわけではありません。
例えば動物取扱責任者に登録されている社員が、資格は取得したものの実は生体の管理をせず、事務作業しかしていなかったということもありえるわけです。
今後の法改正によって、取り扱われる生き物はもちろん、購入した飼い主にとって悲しい事態が起きないよう、さらなる法改正があることを願います。
爬虫類の販売を自宅で行いたい場合は?
今回は繁殖させた爬虫類を販売する、という前提で、どういった流れで動物取扱責任者になるのかを解説します。
あくまで私が行うのであればという例で話を勧めますので、各個人の状況によってはこれ以外の方法があるかもしれないので、やはり所管の動物管理センターに問い合わせたうえで準備を始めることを強くお勧めします。
動物取扱業に登録しているショップで働く
実務経験を得るために、まずは動物取扱業に登録しているショップで働きましょう。
これは対応する動物でなければいけないので、爬虫類を販売するなら爬虫類を販売しているショップにペット専従で勤めましょう。
この専従というのが大事で、例えば犬猫も扱っているショップで、犬猫の餌の担当になってしまうと実務経験として認められない場合があります。
また、実務経験を証明するときに2つ落とし穴があります。
もしすでに実務経験がある方のなかで、平成18年以前の実務経験の場合。
平成18年以前は現行の制度はなかったため、実務経験として認められない可能性が高いです。
この場合、新たに半年間の実務経験を積まなければいけません。
もう一つが、退職するときに「実務経験証明書」を貰わなければいけないということです。
これを貰っていないと、やめた職場に書いて貰いに行くという気まずい思いをしなければいけません
また、ほとんどの場合快く書いてもらえると思いますが、書かないからどうということはないので、意地悪な職場ではスムーズにもらえないかもしれません。
ブリーダーになるために勤める場合は、なるべくホワイト企業に勤めたほうがいいかもしれませんね。
該当する資格を取得する
これまでは実務経験のみで動物取扱業の登録を行えましたが、現行の法律では該当する資格を取得、もしくは該当する事業についての知識が学べる学校を卒業することが必要となりました。
条件を満たす学校等を卒業していない場合、新たに知識を証明できる資格を取得しましょう。
爬虫類ブリーダーを目指す場合、「愛玩動物飼養管理士」が一般的で、動物取扱責任者の要件を満たす資格として広く認められています。
他にも様々な資格がありますが、業種等に応じた資格でなければ対象にならないため、あらかじめ問い合わせて確認しておきましょう。
条件を満たした飼養施設の準備
販売等を行う場合、趣味で飼育しているのと違い、施設と設備を整えなければいけません。
施設に関しては自宅でも条件が揃えば可能ですが、賃貸契約の場合、管理会社や大家から動物取扱業を始める許可がなければ申請はできません。
もし新たにテナントなどを契約するのであれば、あらかじめ動物を販売するために契約する旨を伝えて、必ず了承したという旨を書面での証明を貰える物件を探してもらうようにしましょう。(ないと登録できません)
持ち家の場合に関しては、設備さえ整えればいいというわけではなく、家の場所が事業を行っていい場所なのか、条例で動物の取り扱いを禁止されていないかもあらかじめ確認しておくようにしましょう。
設備に関しても、棚にケージを並べただけでいいというわけではなく、生体にも人間にも安全な設備が整っているか、立ち入り検査があります。
例えば脱走を想定した場合に、すぐに屋外に逃げてしまうような設備だと許可が下りなかった例があります。
これに関しては基準が業種や扱う生体の種類によって違うので割愛しますが、ペットとして飼育していた時とは違う設備が必要になり、建物の構造上対応できなかったり、設備を整えるためにそれなりに予算がかかるということは覚えておきましょう。
役所等へ登録へ
実務経験を積み、資格を取得し、設備を整えたら、所管の役所等へ動物取扱業の申請しに行きます。
基本的には各自治体の動物管理センターになりますが、一部市役所で受け付けているとの話もあるので、あらかじめ窓口を確認しておいた方が安心です。
登録に際して、結構な枚数の書類を用意していかなければいけません。
登録申請書やら実施の方法を証明する書類やら登録要件を満たしている誓約書?やら事業所の証明書やら施設の平面図やら登記簿やら実務経験証明書などです。
忘れると後々面倒になるので、これもあらかじめ問い合わせて準備しておきましょう。
書類に不備がなければ動物管理センターの職員さんなどが立ち入り検査し、問題がなければ登録証を交付してもらえます。
登録に際して1つ注意するべきなのが、自治体によってはあなたの住所や氏名がインターネット上に晒されてしまうリスクがあるということです。
実は動物取扱業に登録すると、法律で登録者の住所や名前、事業所の場所などなどの情報を一般に開示しなければいけないという決まりがあり、いずれにせよ人の目に触れることにはなるのですが、一部の自治体はなぜかそれをインターネット上にも公開し、登録者の住所といった個人情報まで掲載している場合があるのです。
なお法人として開業している場合には、法人の登記簿上の住所(店舗や事務所等)でも申請できる場合もあるので、申請前に確認しておくといいでしょう。
まとめ
今回は、増やした爬虫類を販売したいという場合に必要になる動物取扱責任者についての解説でした。
もちろん詳細は所管の役所等へ確認しておくとが安心ですが、基本的な流れは紹介した通りかと思います。
実務経験と、2020年6月の改正で資格の取得が必須になったことでやや間口は狭まっていますが、無許可の販売は罰則もありますし、今後登録したい場合に許可が下りなくなってしまうこともあるので、安易な販売はぜったいにやめましょう。
日本は愛玩動物関係の法規制が甘く、今後も厳格化されることが予想されますし、売ろうと思い立ってすぐに許可が取れるものではありません。
爬虫類の繁殖は自分ですべて飼育することを前提に行うのが望ましいですね。
やさしい熱帯魚さんサテライトでは今後も爬虫類関係、生体の販売についてのノウハウを紹介していきますので、興味がある方はぜひまた遊びに来てくださいね。